次回は是非参加して下さいね ― 2006年12月14日 23時52分49秒

高プロのお友達です。当然女子プロです。
今回は宴会だけですが次回は是非F-cupにも参加してください。
いつも元気です ― 2006年12月14日 23時54分38秒

今回一緒に回りました。
元気な笑顔です。
もう夜中の1時です。。。。準優勝 ― 2006年12月16日 01時09分18秒
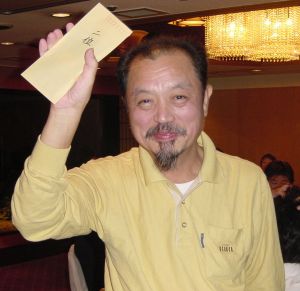
みなさんの期待を大幅に裏切って(^_^) 準優勝してしまった「酔拳」ならぬ「酔ショット」の第三国人です。
米原ゴルフ倶楽部のお昼 ― 2006年12月16日 22時37分58秒

米原のお昼定食・・・天ぷらと刺身定食
この時点では優勝の目も無くなって飲んだビールと共に美味しいかった。
INは高プロのショットに圧倒されっぱなし。。。
分かったのは・・・スイートスポットで打てばいいんだ(^_^)
F-cup 11位で~す ― 2006年12月16日 22時43分30秒

当月賞でもらった11位
F-cup ;美味しい食事と楽しい仲間 ― 2006年12月16日 22時47分33秒

色々あっても終わってみれば楽しい宴会と美味しい料理
今回は騒いでも大丈夫でした(^_^)
のむけはえぐすり 第40弾 原善三郎の話 その20 旧正金銀行(3) ステンドグラス ― 2006年12月19日 00時08分10秒

のむけはえぐすり 第40弾
原善三郎の話 その20 旧正金銀行(3) ステンドグラス
洋銀を、開港記念館(旧英国領事館)で見ることができた。二階展示室のケースに、一円銀と一緒に洋銀が2枚並べられていた。直径が4cm程、厚さが2mm程で、貨幣としてはかなり大きく、意外に薄かった。表には頭を左に向けた鷲が描かれ、裏の模様は黒ずんでよく分からない。黒い錆が、銀であることを証明していた。
娘はその洋銀が高騰した原因を、自分が発行した過剰な紙幣の流通がもたらしたインフレと輸入超過によるものと考えずに、外国商人による投機的取引によると考えた。そこで、適正な洋銀の取引ができるように、明治12年に横浜に洋銀取引所を設立した。だが、逆に投機目的に利用されてしまった。
次に、銀が市場にあふれれば銀が安くなると考え、持っていた銀を市場に放出したが、砂に吸い込まれる水のようにどこかに消えてしまった。
あくまで銀貨高騰の原因を銀貨不足にあると考えた娘は、大蔵卿大隈重信さんや福沢諭吉さんと相談して、銀貨の需要を調整する正金銀行を設立することにした。娘を助けてくれる「正金」さんは、初めは貿易一円銀を中心とする銀貨の供給と、正金銀のまともな相場を作り出すことが目的で設立された。
発起人には中村道太さん、早矢仕有的さんほか、華族士族、銀行家22人がなった。そこには、原善三郎の名はない。私はその理由を、国立第二銀行の経営で余裕がなかったからだと考えている。
明治13年、政府出資の正銀100万円と一般株主の正銀40万円、紙幣の160万円を資本金にして、正金銀行が本町4丁目58番に設立され、半年後に現在地に移転した。
初代頭取は中村道太さんだが、横浜に知る人は少ない。中村さんは、早矢仕有的さんが横浜で創業した丸善の社長だった。
丸善の創業者の早矢仕さんは、美濃から上京して医業を営むかたわら、経済学に興味を持ち、福沢諭吉さんに師事した。当時横浜で流行した梅毒の治療に当たるために尾上町に居を構え、そこで洋書の輸入を始めた。その後福沢さんの薦めで、弁天町に洋書や文具を商う丸善を創業し、東京の銀座に進出した。日本で最初に株式会社となり、今も丸善書店として存続している。
早矢仕さんは区会議員、県会議員になった時、ガス局事件で高島嘉右衛門さんと対決した正義感の強い人で、官権の横暴に立ち向かった自由民権運動のはしりのような人でもあった。
1836年に生まれた中村道太さんは、やはり福沢諭吉さんに紹介され、丸善に入社し、早矢仕さんに引き立てられて社長になった。丸善を辞めた後も、正金銀行の頭取になるまでの数年間は、生まれ故郷の豊橋に戻り、国立第八銀行の頭取をしていた。
正金銀行を辞めた後の中村さんは、東京米商会所の頭取になったが、立憲改進党の大隈重信さんに資金を流用したことで失脚してしまった。
頭取も何代か代替わりし、1902年から正金銀行は借款を担当し、大陸に足がかりを築いた。日露戦争の戦費調達では外債発行に活躍し、海外に支店を展開するようになった。いつの間にか、為替銀行としては、香港上海銀行やチャータード銀行と並び称されるまでに成長した。
写真は、旧正金銀行のエントランスルームの天井のステンドグラスである。そこには、娘が子供の頃に憧れたアニメの美少女戦士セーラームーンの魔法の杖のような模様が放射状に描かれている。セーラームーンは、「月に代わってお仕置きヨ」と呪文を唱え、人々を困らせる欲張りな大人達を、その杖で懲らしめていた。
娘が「正金」さんに助けられ、外国商人にお仕置を果たした時から、娘は自分がされて厭だったことを、今度は大陸の娘達にするようになった。オバサンになった娘は「月に代わってお仕置き」されるまで、そのことに気づかなかった。
参考文献
1)土方晉:横浜正金銀行(戦前円の対外価値変動史)、東洋経済印刷、東京、1999
2)谷内英伸:横浜謎とき散歩 異国情緒あふれる歴史の街を訪ねて、廣済堂、東京、1998
Photo albumつきました ― 2006年12月22日 22時17分02秒
お気づきでしょうか?
左にPhoto albumがつきました。
asabloの写真は小さいのでもっと大きい写真を見せたいので今方法を考えているところです。その一つの方法がこれなのですが。。。(このアルバム形式じゃなく元に行くと大きく見えるんです)
方法は簡単--気に入った(?)写真をクリックすると元の写真にぶちあたります。
ただ容量が30Mしかないからちょっと考えてます。
GoogleのBloggerあたりがいいのかも?と思って調べております。
乞うご期待!
氷川丸とマリンタワー ― 2006年12月23日 20時04分48秒

横浜名物だった氷川丸とマリンタワーが12月25日(月)をもって営業を終了するという。
実は僕は北海道から受験で横浜に来たときに氷川丸に泊まったのである。(宿泊設備があって受験シーズンは旺文社の「蛍雪時代」等で宿泊予約が出来たのである。安かったのと他に探しようがなくてここにした)
船の塗料の臭いがぷんぷんする船内でした。
それで前日にマリンタワーに登ったのである。
あのころから「あこがれの横浜」でした。
氷川丸のおかげかどうかは知らないが合格した。
その両施設に創業以来、「マリンタワー」に2526万人、「氷川丸」に2261万人、両施設合計4787万人の方々が来たという。1人/2,0000万人の一人としてちょっと感慨です(^_^)
のむけはえぐすり 第41弾 原善三郎の話 その21 旧正金銀行(4) 白壁の廊下 ― 2006年12月26日 04時02分04秒

のむけはえぐすり 第41弾
原善三郎の話 その21 旧正金銀行(4) 白壁の廊下
明治14年、娘もようやく、自らのインフレ政策の失敗に気づいた。損ばかりしていた殖産事業を民間に譲渡し、緊縮財政へと舵を切り替えた。その責任をとって、大隈重信さんは大蔵卿を辞めた。
No2だった松方正義さんが大蔵卿になると、さらに徹底した不換紙幣の整理が始まった。財政を引き締め、増税をして、どうにか財政を黒字化することに成功した。5年間で1364万円もの紙幣を、文字通り焼き捨てた。
反面、松方さんの超デフレ政策によって、世の中は不況になり、金融機関の倒産が相次いだ。生糸と茶の輸出前貸と為替を扱っていた正金銀行も、その煽りをもろに食った。
正金銀行の存続が危ぶまれたにもかかわらず、初代頭取の中村道太さんと二代目頭取の小野光景さんの動きは鈍かった。仲間の横浜商人の窮状に、目が奪われ過ぎたのかもしれない。
そこで明治16年、エール大学で経済を学び、イギリスでレオン・レヴィに師事した第百銀行の頭取原六郎さんが、正金銀行の四代目頭取に迎えられた。原六郎さんは、改革に反対する株主を排除し、潰れるべきところは見捨て、改革のスピードを速めた。
すでに、資本金300万円に対して、不良債権は約180万円にのぼっていた。原六郎さんは、まず資本金を切り崩して損失を補填した。そして、資本金を銀貨ではなく通貨にし、為替取組の支払利息を正金銀行の収入にするように法律を変えた。そうやって足腰を鍛えてから、外国商人に対する輸出為替の取扱も始めた。
3年後には、正金銀行の為替取扱高は、530万円余から2500万円余に急増した。生糸の輸出取扱高の四分の三を扱うまでになった。正金銀行の性格は、紙幣整理ではなく、為替関連の業務へと変わっていった。
そこで本来の紙幣整理を目的として、日本銀行が明治15年に設立された。初代総裁には正金銀行関係から吉原重俊さんが就任した。松方さんはある書簡の中で、「日本銀行は内国を経理して以て外国にあたり、正金銀行は海外を経理して以て内国を益し・・・」と書き送っている。要するに、娘のために、独立した立場で、お互いを尊重して、相互補完の良い関係でやっていきましょうと、正金銀行と日本銀行の役割分担を明確にした。
当時横浜の外資系銀行は、イギリス系の東洋銀行、香港上海銀行、チャータード銀行と、フランス系のコントワ-ルデスコンテ銀行が活躍していた。その中の東洋銀行が娘の海外での資産運用を担当していたが、明治17年に破産した。正金銀行は東洋銀行に代わって、自らロンドンでの銀取引に参入することになった。それが始まりとなって、海外支店を増やしていった。
明治18年には、娘の借金は全額返却され、紙幣と銀貨の格差も解消した。日本銀行はこの時から、兌換紙幣の日本銀行券を発行するようになった。
その後、正金銀行は世界の三大為替銀行に成長した。だが、昭和20年の敗戦によって正金銀行の100以上あった海外支店は接収され、膨大な在外資産を失った。
昭和22年6月、正金銀行の勘定は東京銀行に譲渡され、戦前に世界最大の為替銀行と目された正金銀行の歴史を閉じた。
写真は、馬車道の玄関から入った旧正金銀行の廊下である。どんよりとした薄明かりに照らされた漆喰の白壁の廊下を、原六郎さんは歩いた。窓もない、飾りっ気ひとつない廊下は、立ち止まることが許されなかった原六郎さんの心象風景のようだ。
結論をいえば、紙幣を発行する「国立」銀行の153は多すぎた。
窓があって外を見れば、中村さんや小野さんのように立ちすくむ。原六郎さんが立ち止まったら、その後の正金銀行も娘もなかった。

最近のコメント